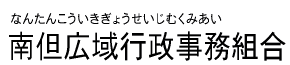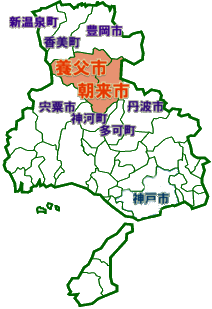農業経営収入保険事業の創設について(お知らせ)
|
1.収入保険を検討中の皆様へお知らせ 2.収入保険制度の周知活動について 3.収入保険制度の概要について 4.農業者のみなさん、青色申告を始めましょう! 5.国・県情報にリンク |
農業災害補償法の一部を改正する法律(平成30年4月1日施行予定)に伴い、現行の法律名「農業災害補償法」が「農業保険法」に改められます。
また、本法律(改正)に基づき、「農業経営収入保険事業」が創設され、平成31年度産の農産物より導入される予定です。
共済制度の改正については、農林水産省ホームページ(※下欄リンク)により確認してください。
1.収入保険を検討中の皆様へお知らせ
個人及び12月決算の法人の収入保険の加入申し込みは、11月末日までとなっておりましたが、全国農業共済連合会から「12月末まで1ヶ月間延長する」との通知がありましたので、お知らせいたします。
平成30年は台風や大雨、地震等の災害多発により、農業者様への十分な加入検討期間がなかったことによる今回の措置となりました。
十分ご検討いただき、加入相談等につきましては農業共済課までお願いいたします。
2.収入保険制度の周知活動について
- 南但広域行政事務組合・農業共済課では農業者等の皆様を対象にした「収入保険制度説明会」を開催しています。
- 農家の皆様で収入保険制度の詳細をお知りになりたい方は、遠慮なく農業共済課にお電話を頂くか、又は直接お越しください。
- 農業者等の皆様で組織している団体で、収入保険制度に関する説明会の開催を希望される場合は、農業共済課までご連絡をお願いします。
 |
 |
|
| 平成30年2月28日 朝来会場説明会 | 平成30年3月1日 養父会場説明会 |
3.収入保険制度の概要について(農林水産省資料より抜粋)
対象者(保険資格者)
- 青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者(個人・法人)が対象となります。
- 青色申告を5年間継続している農業者を基本とされていますが、制度導入時においては、青色申告(簡易な方式を含む。) の実績が加入申請時に1年分あれば加入可の対応を行なうこととされます。
- 加入は農業者の選択(任意加入)によります。
対象収入
- 収入保険制度では、農業者が自ら生産している農産物(農産物を簡易な加工をしたものを含む。)の販売収入全体が対象となります。
- 経営コストについては合理的な確認が難しいため、収入保険制度では「農業者の所得」ではなく、「農業収入金額」を対象としています。
補償内容(制度の上限額)
- 補填の基準となる基準収入については、農業者ごとの過去5年間の平均収入とすることを基本とします。
- 基準収入については、農業者の経営規模の増減等により上方修正又は下方修正することが出来ます。
- 収入保険制度では、当年の収入が基準収入の9割水準(※「保険方式+積立方式」で加入時は9割。「保険方式のみ」で加入時は8割となります。)を下回った場合に、下回った額の9割の補填金を支払うことなります。
保険料・積立金
- 「掛捨ての保険方式」と「掛捨てとならない積立方式」の組み合わせを基本としています。
※保険料は掛捨てになります。
※積立金は自分のお金であり、補填に使われない限り、翌年に持ち越されます。 - 補償限度額及び支払率は、農業者が保険料負担を勘案して補償内容を選択することとなります。
- 「積立方式」への加入については、農業者が選択できます。
- 保険料=基準収入×補償限度(8割を上限に選択)×支払率(9割を上限に選択)×保険料率(国庫補助後1%)
- 積立金=基準収入×積立幅(1割)×支払率(9割を上限に選択)×1/4
- 農業経営収入保険の保険料の50%を、積立方式による補填の75%を、それぞれ国が負担します。
収入保険制度の実施
- 収入保険制度は、平成31年1月からスタートします。
現在実施している類似制度との関係
- 収入保険制度と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度は、どちらかを選択して加入することになります。
4.農業者のみなさん、青色申告を始めましょう!
詳しくは、下記のチラシをご覧下さい。
青色申告を始めましょう!(農林水産省チラシ)